 はじめに
はじめに 今、注目されている天然水素(Ⅳ)
天然水素への「エネルギー変革」の第一歩は、”良好な天然水素鉱床”の発見である。とにかく、高純度な天然水素が豊富に回収できる天然水素鉱床が1カ所でも発見されると、「エネルギー変革」は加速的に進むことを過去の例が示している。資金の豊富なメジャーが動くと本格化する。それまでスタートアップ各社の頑張りに期待したい。
 はじめに
はじめに 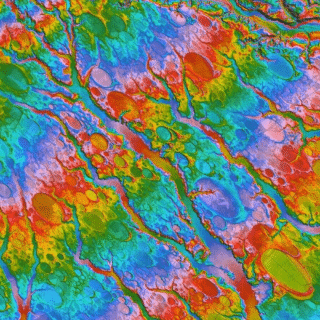 はじめに
はじめに 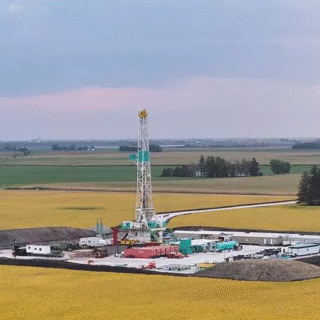 はじめに
はじめに  はじめに
はじめに  はじめに
はじめに  エネルギー
エネルギー  エネルギー
エネルギー  自動車
自動車  船舶
船舶  船舶
船舶