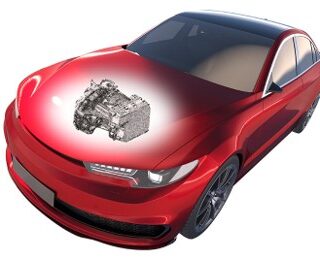 自動車
自動車 eアクスルとは?
EVの基幹部品である「蓄電池」は、蓄電池メーカーとの連携が進められている。一方、「駆動装置」については、インバータ、モーター、ギア(減速機)の3要素を一体化した「eAxle(eアクスル)」メーカーが立ち上がり、EVの開発期間短縮を可能とし、EV事業への参入障壁を下げている。
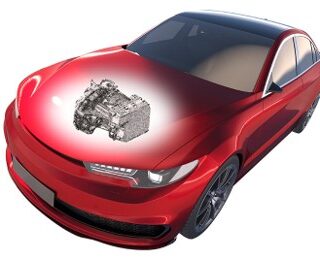 自動車
自動車  航空機
航空機  自動車
自動車  いろいろ探訪記
いろいろ探訪記  航空機
航空機  航空機
航空機  航空機
航空機  原子力
原子力 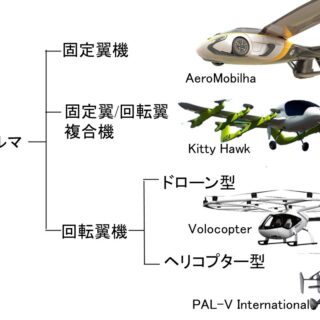 航空機
航空機  航空機
航空機