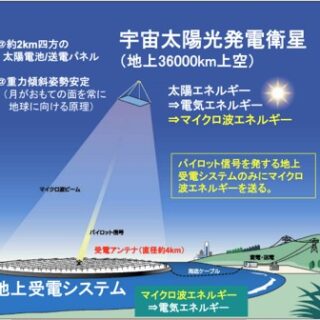再エネ
再エネ なぜ?再燃する宇宙太陽光発電(Ⅳ)
2022年11月、ESAはSSPSの実現可能性を本格的に調査するプロジェクト「SOLARIS(ソラリス)」をスタートさせた。また、2021年には英国を拠点とするエネルギー、宇宙、材料、製造の研究・企業連合「Space Energy Initiative」が設立され、「CASSIOPeiA」計画が推進されている。 中国では宇宙技術研究院(CAST:Chinese Academy of Space Technology)を中心に、SSPS研究が推進されている。